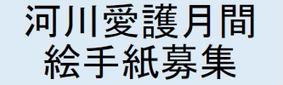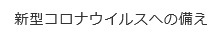エッセー
アテネへの道
|
宇津木 妙子(うつぎ たえこ) アテネオリンピック |
|
「全ての道はローマに通ず」 この有名な言葉は、かのフランスの詩人、ラ・フォンテーヌによるものである。これは、ローマ帝国全盛期、世界中のすべての道がローマに通じていたということから、物事が中心に向かって集まること、また、やり方は違っていても、目的は同じであること、また、物事が一つの真理から発していることのたとえ(広辞苑より)である。
私たち女子ソフトボール日本代表チームは、All roads lead to Athens.「全ての道はアテネに通ず」の思いで、この4年間という日々を、ただひたすら金メダル獲得のためだけに費やしてきた。しかし、このアテネまでの長い道のりは、私たち全日本チームにとって決して平坦で歩きやすいものではなかった。
「限りなく金メダルに近い銀メダル」と評されたシドニーオリンピックでの戦いは、まだ皆の記憶に新しいものだと思う。予選リーグを7戦全勝で突破し、決勝で王者アメリカと戦うまでの日本チームの快進撃は、「日本に女子ソフトボールありき」を内外に広く、そして強くアピールするほどのものとなった。
だが、延長8回裏でのまさかの敗北。アメリカチームの歓喜のホームインを茫然として見るだけの私たち。あの光景を私は今も忘れることが出来ないのである。
私にはあの時、あの瞬間に、あたかも時が止まってしまったかのように思われた。「シドニーまで」と心に決めて、代表監督を辞す覚悟であった。「もうこれ以上のことはできない。」との思いでやってきた4年間だったのである。
しかし、投手交代の躊躇が招いたこの結果に、私には悔しさだけが残った。「金メダルに近い銀メダル」では納得が出来ない自分がいた。もしこれが決勝へ進めずに銅メダルだったら、そして、もし決勝で1点も取ることが出来ずに負けていたら、潔く諦められたであろう。
シドニーオリンピックでのこの経験が「アテネで金メダルを!」の強い思いにつながっていたのである。
「もう一度金メダルに挑戦してみるか!」この思いを消せない一方で、自分自身には迷いがあった。オリンピックまでの4年という長さに加え、また一から全てやり直すことへの不安もあった。それにはかなりのエネルギーが必要であるし、それ相応の覚悟もいる。周囲の期待も感じてはいたが、なかなか踏ん切りがつかないでいた。
しかし金メダルを確実に狙える位置にいて、それを声に出来るものが一体何人いるだろうか。そんな幸運が巡って来ることなどそうそうない。シドニーでの悔しさを晴らし、選手たちの胸に金メダルを!という思いが、日に日に募って行った。
「自分の好きなように、信じるようにやればいい。」と言って、迷い続けていた私の背中を最後に押してくれたのが主人だった。代表監督であればチームのことが最優先になり、帰りも遅い。海外遠征や合宿で家を留守にすることも多くなる。それらを全部理解してくれた上でそう言ってくれたのだ。
こうしてこのあと、私のアテネまでの続投が全会一致で決まったのだった。私は周囲の人、そして主人に感謝の気持ちでいっぱいだった。これでなんの迷いもなくソフトボールに没頭できる。
「シドニーで足りなかったものは何か?」シドニーオリンピックの反省を活かさなければ、また同じことの繰り返しである。
私自身が一番感じていたことは「投手力」である。世界のトップクラスが時速110キロ超の球を投げ、ライズ、ドロップを駆使する中で、日本の投手は時速100キロにも満たない球速で、球種も少なく、コーナーワークと緩急で勝負をするしかないのが現状である。ソフトボールの場合、投手の力が試合の7~8割を決めると言われる。好投手なきところにメダルもないのである。
また、野手も宇津木麗華選手をはじめ、ベテラン選手の年齢的な問題もあった。女性アスリートにとって、4年という歳月はかなり長い。そしてずっしりと重いものなのである。
シドニーチームが完成品だとすると、アネテのチーム作りはどのようにすべきなのか。一から全てを模索するところから、私のアテネへの挑戦が始まった。
「投手力の強化」という最大の課題と思われたものが、簡単にクリアされた。上野投手の出現である。彼女の投げる球は、時速110キロ。「オリエンタル・エクスプレス」の異名をとったのはわずか高校2年生の時だった。この若い逸材を、自分のこの手で育てることが出来るのは、指導者として大きな喜びだった。
上野投手の出現により、私の中で一気にアテネチームの青写真が出来つつあった。
シドニーのチームが「良いチーム」だとしたら、アテネのチームは「強いチーム」にしなければならない。
シドニーでは自分を犠牲にしてもチームのことを優先出来る選手を意識的に選んだ。その結果が「銀」である。このチーム以上のチーム作りをしなければ「金」は望めない。
そのためには、ハッキリと自己主張が出来る選手、チームのために自分を活かせる選手、ここという時に「自分が決める」と迷わず言える強さを持った選手を育てていかなくてはならない。
「個の強さ」を持ったチームにしたい。ソフトボールはチームスポーツといえども、局面ごとに問われるのは「個人」の能力なのである。
私の考えの根本に、リーダーとは最終的には「人を育てること」である、という考えが常にある。チーム作りはイコール人作りなのである。これはスポーツだけに限らないと思う。全てに共通するものではないかと考えている。企業においても、学校においてもそうなのではないか、と。心がなかったら人は動かない。ハード面(技術)とソフト面(心)をバランスよく指導することにより、シドニー以上のチーム作りが可能になるのではないか。
シドニー等のオリンピック経験者と、若手の育成を図りながらのチーム作りを念頭に入れての選手選考となったこのオリンピック。それはまず、私の心の中のシドニーの記憶を完全に拭い去ることから始まったのだった。
日本潰しと言われたルール改正(投球距離が約1m延びた等)や、SARSの大流行による海外遠征の中止などを乗り越え、37名の日本代表候補選手を最終メンバーの15名に絞りこんだ。100名を超える報道陣が集まる中、代表メンバーの発表が行われた。シドニーの時とは明らかに違う雰囲気。期待されているというのは、こういうことなのか。代表選手と関係者に手紙を渡し、「いざ、アテネへ。」8月3日、私たちは日本を発った。
そしてその20日後。アテネのスタジアムのスタンドから決勝を観戦する私たちがいた。アメリカと戦うのは私たちではなく、前日負けたオーストラリアであった。「アテネで金メダルを!」と、ことあるごとに言い続けて来た私だが、それは「アメリカに勝って」金メダル、という意味なのである。しかし、予選4日目で1勝3敗。あとひとつ負けたら予選落ちというギリギリの状況から4連勝しての銅メダルは、チームの底力を出せた結果でもあるし、充分評価に値するものだと思う。日本における球技競技で、オリンピック2大会連続のメダル獲得は唯一のものなのである。
それにしても選手たちはよく頑張ってくれた。ベストをつくして戦った。ここまでやれたのも選手やスタッフ(水泳のチーム北島同様のサポート体制が組まれた)のおかげである。私自身もイギリスのクレック監督からの手紙の中の「楽しみなさい。」「あなたは世界の8人の監督の中のひとりなんだよ。」という言葉に元気づけられ、どれだけ気持ちを楽にすることが出来たであろうか。シドニーの後、駅や街などで「頑張って」「負けないで」と声をかけられる機会が多くなったのだが、こういった何気ない言葉にどれだけ勇気づけられたことか。私たちは知らないところでたくさんの人たちに支えられてここまできた。感謝の気持ちを忘れてはいけないのである。
自分を信じ、何より選手を信じて「金メダル」という夢をもとめて挑戦してきたこの4年の歳月。残念ながらアテネでは叶わぬ夢となってしまった。しかし、「シドニー発アテネ経由北京行き」の列車はこの大きな夢を乗せて、新たに走り出したのである。この夢を叶えることは、ソフトボールに携わる者の悲願である。監督として、あるいは全日本の選手としてだけの夢だけではない。
私自身もいつまでも夢を追い続けて行きたい。どのような形でそれに関わっていけるのか今はわからないが、どんな時でもソフトボールを愛し、ソフトボールとともに人生を歩んで来た私には、夢の続きがはっきりと見えるのである。「北京」の表彰台に。